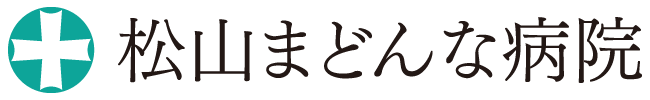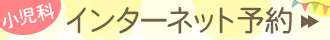選択項目検査
別途料金が必要になりますが、人間ドックや一般健診に追加できる検査項目です。選択項目の中には、検査結果が判明するまでに10日前後かかる検査も含まれています。ドックを受けない方でも選択項目のみの受検も可能です。なお、選択項目申し込み時には別途文書代 1,000円(税別)がかかります。
選択項目は自由に組み合わせていただいて構いません。気になることがあるけど検査をどう組み合わせてよいか分からない方は、スタッフにご相談ください。選択項目は全て予約検査になりますので、健診をお申し込みの際にお申し出ください。
選択項目検査と料金
| 検査項目 | 費用(税別、単位:円) | |
|---|---|---|
| がん検診 | 子宮頸がん検査(内診、細胞診、超音波検査) | 3,000 |
| マンモグラフィー | 5,000 | |
| 胃部X線 | 13,000 | |
| 胃内視鏡(感染症別途) | 14,000 | |
| 腫瘍マーカー | CEA(大腸がんの検査) | 2,100 |
| AFP(肝がんの検査) | 2,100 | |
| PIVKA-Ⅱ(肝がんの検査) | 2,500 | |
| CA19-9(膵がんの検査) | 2,500 | |
| エラスターゼ-1(膵がんの検査) | 2,400 | |
| PSA(前立腺がんの検査) | 2,400 | |
| CA15-3(乳がんの検査) | 2,100 | |
| CA125(子宮がんの検査) | 2,600 | |
| SCC抗原(子宮・食道・肺がんの検査) | 2,100 | |
| シフラ(肺がんの検査) | 2,800 | |
| がんリスク検査 | ||
| アミノインデックスリスクスクリーニング検査(AIRS検査) | 22,500 | |
| ABC検診(ペプシノゲン+ピロリ菌抗体) | 4,500 | |
| CT検査 | 頭部 | 13,600 |
| 胸部 | 14,600 | |
| 腹部 | 15,200 | |
| 内臓脂肪測定(腹部CTあり) | 2,000 | |
| 内臓脂肪測定(腹部CTなし) | 3,000 | |
| MRI検査 | 簡易脳ドック検査(頭部MRI+頭部MRA+頸部MRA) *脳ドック単独での検査申し込み不可 |
20,000 |
| 全身MRIがん検診(DWIBS(ドゥイブス)検査) *全身MRIがん検診単独での検査申し込み可 |
50,000 | |
| 血液型 | ABO型、Rh型 | 500 |
| 感染症 | 肝炎ウイルス検査(HBs抗原・抗体、HCV抗体) | 2,930 |
| HIV(エイズ検査) | 3,000 | |
| 眼 | 眼圧検査 | 1,000 |
| 眼底検査 | 700 | |
| 耳 | 簡易聴力検査 | 500 |
| 甲状腺 | 甲状腺超音波検査 | 3,000 |
| 甲状腺機能検査(TSH、FT3、FT4) | 6,000 | |
| 呼吸器 | 胸部XP | 2,000 |
| 肺機能検査 | 1,600 | |
| 循環器 | 心電図 | 1,500 |
| 血管年齢検査 | 1,500 | |
| 頚動脈超音波検査 | 3,500 | |
| 胃 | ペプシノゲン検査 | 2,000 |
| 血中ピロリ菌抗体検査 | 2,500 | |
| 大腸 | 便潜血(2回法) | 1,600 |
| 肝・胆・膵 | 腹部超音波検査 | 5,300 |
| 更年期検査 | FSH、LH、エストラジオール | 5,940 |
| 骨 | 骨密度(骨粗鬆症) | 1,400 |
| 脳梗塞・心筋梗塞 発症リスク検査 |
ロックス・インデックス検査 (LOX-index検査) |
12,000 |
| 認知機能 | 認知機能セルフチェッカー | 3,000 |
検査内容
子宮頸がん検査
内診と細胞診の検査をします。内診は、子宮、卵巣、膣などを医師が診察します。細胞診は子宮頚部や内膜の細胞を綿棒でこすって採取し、顕微鏡でがん細胞の有無を調べます。ドック健診の方は超音波検査も同時に行っております。子宮がんには、子宮の入り口部にできる子宮頸がんと、子宮の奥の部分にできる子宮体がんがあります。子宮体がん検査をご希望の方は、婦人科受検時にお申し出ください(別途料金必要)。
- 子宮がん・卵巣がんが心配な方は、子宮がん細胞診検査に、子宮がんや卵巣がんで上昇する腫瘍マーカーのSCC抗原とCA125を追加検査されるといいでしょう。
マンモグラフィー
乳房専用のX線装置を用い、乳房を片方ずつ、上下、左右の2方向からそれぞれ板で挟んだ状態で撮影します。乳房を圧迫するため多少の痛みがある場合がありますが、視触診だけでは発見できないしこりや石灰化といわれるカルシウムの沈着など、乳がんに特徴的な所見をとらえることができます。乳房超音波検査と併用すると診断精度がさらによくなります。乳がんの早期発見のために、40歳以上では、2年に1度のマンモグラフィー検診が勧められています。
胃部X線
食道・胃・十二指腸の内面を造影して調べる検査です。飲み込んだバリウムの流れや内面に付着したバリウムをX線でみることで、消化管の内面の突起(腫瘤)やくぼみ(潰瘍)の有無がわかります。
胃内視鏡
口から内視鏡(胃カメラ)を入れ、食道・胃・十二指腸の内面を直接観察する検査です。バリウム検査では分からない小さな病変の発見に有効です。病変が見られた場合、病変の一部を採取し病理組織検査を行うこともあります。
腫瘍マーカー
がんができると、健康な時には見られない特殊な物質が産生されて血液の中に出現します。これらの物質を測定することにより、がんの経過や診断の手がかりとします。臓器特有のものとそうでないものとあるため、いくつかを組み合わせて検査します。早期のがんがあっても腫瘍マーカーが上昇しないこともあります。レントゲン検査、CT検査、超音波検査などの画像検査と組み合わせて検査されることをお勧めします。
| CEA | 大腸がんの指標となる腫瘍マーカーです。各種のがんでも上昇します。加齢や喫煙などでも上昇します。 |
|---|---|
| AFP | 肝細胞がんの指標となる腫瘍マーカーです。 |
| PIVKA-Ⅱ | 肝細胞がんの指標となる腫瘍マーカーです。 |
| CA19-9 | 膵・胆嚢がんの指標となる腫瘍マーカーです。膵炎などでも上昇することがあります。 |
| エラスターゼ-1 | 膵がんの指標となる腫瘍マーカーです。 |
| PSA | 前立腺がんの指標となる腫瘍マーカーです。前立腺炎や前立腺肥大症などでも上昇することがあります。 |
| CA15-3 | 乳がんの指標となる腫瘍マーカーです。 |
| CA125 | 卵巣がん・子宮がんの指標となる腫瘍マーカーです。子宮内膜症や子宮筋腫などでも上昇します。 |
| SCC抗原 | 子宮がん・食道がん・肺がんの指標となる腫瘍マーカーです。 |
| シフラ | 肺がんの指標となる腫瘍マーカーです。 |
- 胃がんや大腸がんが心配な方は、胃部X線検査・胃内視鏡検査、便潜血検査に、消化器がんで上昇する腫瘍マーカーのCEAを追加検査されるといいでしょう。
- 肝がんが心配な方は、腹部超音波検査や腹部CT検査に、肝がんで上昇する腫瘍マーカーのAFP、PIVKA-Ⅱを追加検査されるといいでしょう。
- 膵がんが心配な方は、腹部超音波検査や腹部CT検査に、膵がんで上昇する腫瘍マーカーのエラスターゼ-1、CA19-9を追加検査されるといいでしょう。
- 前立腺がんが心配な方は、前立腺がんで上昇する腫瘍マーカーのPSAを検査されるといいでしょう。PSA検査は感度の高い検査ですので、腫瘍マーカーの検査だけでがんのスクリーニング検査になります。男性の方は、50歳を過ぎたらPSA検査を受けることをお勧めします。
アミノインデックスリスクスクリーニング検査(AIRS検査)
アミノインデックス検査は血液中のアミノ酸濃度を測定し、健康な人とがんである人のアミノ酸濃度のバランスの違いを統計的に解析することによって、がんであるリスク(可能性)を評価します。胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん(男性のみ)、膵臓がん、乳がん、子宮卵巣がん(女性のみ)を対象としたリスクについて予測することができます。「ランクA(がんであるリスクが低い)」「ランクB」「ランクC(がんであるリスクが高い)」の3段階に分類されます。がんであるリスクが高いランクCと判定された場合は精密検査が必要です。がんであるか否かをはっきりと判断するものではありませんが、腫瘍マーカーが上昇しない早期のがんが発見されることがあります。また、生活習慣病のリスクスクリーニングとして、10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク、4年以内に糖尿病を発症するリスク、大切な栄養素である必須・準必須アミノ酸が現在血液中で低下していないかどうか、および現在認知機能が低下している可能性(50際以上の方に限る)についても同時に評価します。検査結果の報告に10日から2週間程度かかります。
ABC検診
ピロリ菌の抗体検査と胃粘膜の萎縮の程度を調べるペプシノゲン検査を組み合わせて、胃がんになりやすいかについてリスク(可能性)を評価する検査です。A群(健康的な胃粘膜)、B群(少し弱った胃粘膜)、C群(弱った胃粘膜)、D群(かなり弱った胃粘膜)の4段階に分類されます。C群やD群は胃がんの高リスク群で、C群やD群と判定された場合は胃内視鏡検査による精密検査を受けることをお勧めします。胃がんがあるか否かをはっきりと判断するものではありませんが、C群やD群ではおよそ2%の確率で胃がんが見つかるとの報告があります。また、B群やC群と判定された方は、ピロリ菌感染が疑われます。ピロリ菌感染は胃粘膜の萎縮や胃がんの発生に影響を及ぼすので、胃内視鏡検査を受けて、除菌治療を受けることをお勧めします。
〈下記に該当する方はABC検診の判定ができません。胃透視や胃カメラの検査を受けることをお勧めします〉
・胃の病気治療中の方
・胃切除後の方
・胃酸を抑える薬を服用中の方
・腎不全の方
・ピロリ除菌治療を受けた方
CT検査
CT検査とは、X線を使った多方向から体の断面を撮影する検査です。呼吸による撮影部位のずれが少ないため、微小な病変の発見に有効です。胸部X線では心臓の影になって見えにくい部分もよくわかるため、肺などの病気の早期発見に有効です。腹部超音波検査では胃や腸の影になって見えにくい部位もよくわかるために、膵臓や腎臓の病気の診断精度が上がります。
内臓脂肪測定
内臓脂肪は、お腹の中に貯まる代謝の活発な脂肪であり、高血糖、高血圧、脂質異常などの生活習慣病を起こす大きな原因となっています。特に、内臓脂肪が蓄積し、生活習慣病が重なって引き起こされ、動脈硬化の危険が高まった状態を「メタボリックシンドローム」と呼び、心臓病や脳卒中など命にかかわる病気を招きます(メタボリックシンドロームの診断基準では、内臓脂肪を測定するかわりに腹囲のサイズで代用しています)。診断基準では、男女とも内臓脂肪面積が100cm²以上を危険としています。メタボリックシンドロームと判定された方は、運動と食習慣の改善で、肥満、メタボを解消しましょう。
簡易脳ドック検査
MRI(磁気共鳴映像)、MRA(磁気共鳴血管撮影)検査により、脳の病気(脳梗塞、脳動脈瘤、脳動脈狭窄症、脳腫瘍など)の早期発見に役立てます。頭痛や頭重感が続く、物忘れが気になる、視力の低下や視野の狭さを感じる、日常動作(文字書きや箸使いなど)のできないことがある、親族に脳卒中や脳腫瘍になった方がいる、40歳以上で脳の検査をしたことがない、などの中に気になる項目がある方にお勧めです。
全身MRIがん検診(DWIBS (ドゥイブス)検査)
MRIを使用して体の広い範囲にわたって悪性腫瘍(がんや転移)を探す全身がん検査です。悪性腫瘍が細胞密度の高い(細胞と細胞の間が狭い)ことに着目し、細胞間の水の動きをもとに、拡散協調像という撮影方法を用いて悪性腫瘍を検索します。頸部から胸部・腹部・骨盤を一度の検査で撮影することができます。全身がん検査といえばPET-CTがよく知られています。しかし、PET-CTは被ばくがあり、前処置(検査の準備)で2時間ほどかかり、さらには高額ととても敷居の高い検査です。そこで考案されたのがDWIBS(ドゥイブス)検査です。PET-CTとの比較は下表の通りです。
| DWIBS(全身MRI) | PET-CT | |
| 検査費用 | PET-CTよりは安い | 高い |
| 注射 | なし | 検査薬(放射性同位元素)を注射 |
| 被ばく | なし | 注射薬とCT撮影の2重被ばく |
| 食事制限 | なし | 6時間の絶食 |
| 検査前処置 | なし | 注射後1時間安静 |
| 検査時間 | 1時間程度 | 注射を含め3時間程度 |
| 検査後の処置 | なし(すぐ帰宅可) | 放射能が下がるまで待機 |
| その他制限 | "MRI検査を受けられない方は検査不可 (ペースメーカー・閉所恐怖症等)" |
糖尿病・腎不全の方は 検査できない場合がある |
がん検診を一度に受診したい、数年がん検診を全く受けていない、精度の高い検査を求めている、日頃定期健診のみを受診している、などに該当する方にお勧めです。
*MRI検査の注意事項
検査は原則午後で完全予約制です。一般健診やドック検診を受けられる方は午前に検査が受けられるよう配慮いたします。必ず検査規模日の2週間前までにお電話にてご予約ください。結果は郵送いたします。結果説明を希望される方は後日になりますので、検査当日に説明希望日の予約をお取りください。なお、脳ドック単独での検査申し込みは受け付けておりません。一般健診やドック検診のオプション検査としてお申込みください。全身MRIがん検診(DWIBS(ドゥイブス)検査)は単独でも検査申し込みができます。MRI検査は磁気を使用するため、体内に医療機器等を装着されている方など、検査を受けられない場合があります。ご注意ください。
〈下記に該当する方は検査を受けることができません〉
・心臓ペースメーカーのある方
〈下記に該当する方は検査を受けられない場合があります〉
治療を受けた医師や医療機関に、治療を受けた日付、どのような治療だったのか(身体に入っている金属や異物は何か等)事前にお問い合わせの上、当センターまでご連絡ください。
・人工関節の手術を受けた方
・脳動脈瘤の手術を受けた方
・その他身体に金属(人工関節・クリップ・ワイヤー・インプラント等)の入っている方
・入れ墨をしている方(入れ墨の染料に金属成分を含む場合があります)
肝炎ウイルス検査
肝炎ウイルスに感染していると、肝硬変や肝がんになる危険性が高くなります。B型肝炎の抗原・抗体、C型肝炎の抗体などを調べる検査です。過去に輸血を受けたことがある方、50歳以上の方にお勧めです。
甲状腺機能検査
甲状腺で作られる甲状腺のホルモンなどを調べる血液検査です。甲状腺ホルモンはエネルギー代謝の調節や細胞の新陳代謝を活発にする働きがあります。ホルモンが不足すると、皮膚乾燥、むくみ、寒がり、体重増加など甲状腺機能低下症状がみられます。ホルモンが過剰になると、動悸、発汗、ふるえ、倦怠感、体重減少など甲状腺機能亢進症状がみられます。
- 甲状腺の病気が心配な方、動悸がする方、脂質異常症を指摘されている方、疲れやすくむくみが気になる方は、甲状腺超音波検査に甲状腺機能検査を追加検査されるといいでしょう。
肺機能検査
肺が正常に働いているかどうかを調べる検査です。スパイロメータという器具を使用し、肺活量や1秒量などを測定することで呼吸器疾患の診断や早期発見に役立ちます。1秒量の結果から、肺年齢を推定することができます。喫煙者の方にお勧めです。
血管年齢検査
両腕と両足首の血圧を測る簡単な検査です。心臓からの拍動が足首に届くまでの速度から動脈硬化の程度を調べます。足首と腕の血圧の比から、下肢の動脈に狭窄などの血行障害がないか調べます。
- 動脈硬化が気になる方は、下肢の血管の動脈硬化を調べる血管年齢検査に頚動脈の動脈硬化を調べる頚動脈超音波検査を追加されるといいでしょう。
頚動脈超音波検査
超音波を頚動脈(首の動脈)にあてて、頚動脈の狭窄やプラーク(血管壁に見られる隆起)の有無、頚動脈の壁の厚みを測定する検査です。頚動脈の動脈硬化の程度がわかるので、全身の動脈硬化の程度を推測したり、脳梗塞などの脳血管疾患の危険性などを判定したりする検査です。
ペプシノゲン検査
血液中のペプシノゲンの量を測ることによって、萎縮性胃炎の程度を調べる検査です。ペプシノゲンはたんぱく質を消化する酵素のもとになる物質で、血液中の量が減少すると胃粘膜の萎縮も強くなり、萎縮が強いほど胃がんになりやすいと言われています。萎縮性胃炎・ピロリ菌感染・胃がんなどのスクリーニングに適しています。
血中ピロリ菌抗体検査
ピロリ菌は胃粘膜の萎縮や胃がんの発生に関係しているといわれています。ピロリ菌に感染すると血液中に抗体ができるので、血液検査でその抗体の有無を調べます。胃内視鏡検査を受けない方にお勧めです。ピロリ菌の除菌治療を受けた方は治療後も血液中に抗体が残るので、血中ピロリ菌抗体検査では現在のピロリ菌感染の有無の判定が困難になることがあります。現在のピロリ菌感染の有無を知りたい方は、便中ピロリ菌抗原検査を受けることをお勧めします。
便潜血(2回法)
大腸のポリープやがんからは微小な出血が起きていることがあります。便に消化管から出た血液が含まれていないかどうかを調べる検査です。大腸がんやポリープの早期発見に有効です。事前に容器をお渡しします。便を取っていただき、受検当日御持参ください。
腹部超音波検査
肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓などの内臓の病気の有無を超音波を用いて調べます。胃や腸などの消化管の検査には適していませんので、胃の検査などとの併用をお勧めします。
更年期検査
更年期障害の原因はホルモンバランスの乱れといわれています。ホルモン濃度により、更年期障害が起こっているのかどうかを知ることができます。FSH(卵胞刺激ホルモン)、LH(黄体化ホルモン)、E2(エストラジオール)を調べます。E2(エストラジオール)は女性ホルモンであるエストロゲンの主要成分です。エストロゲンが減ると、脳下垂体前葉から分泌されるFSH、LHが増えるという相関関係にあります。
- 女性ホルモンの低下によって骨密度も低下します。更年期の方には、ホルモン検査と同時に骨密度も調べることをお勧めします。
- 自覚症状が気になる方は、治療が必要となる場合があります。婦人科でご相談されることをお勧めします。
骨密度
骨塩量(骨の中のカルシウムなどの量)を測定し、骨の強度を計る検査です。骨粗鬆症になりやすい閉経後の女性にお勧めです。骨塩量が70%以下の場合、骨粗鬆症と診断されます。
ロックス・インデックス検査(LOX-index検査)
血液中の悪玉コレステロール(LDLコレステロール)が酸化ストレスによって変性した超悪玉コレステロール(LAB)と血管の炎症を引き起こすLOX-1という物質を測定して、将来の脳梗塞・心筋梗塞を発症するリスクを算出します。動脈硬化が進行してしまう前からの予防のための指標としていただける検査です。動脈硬化が心配な方にお勧めの検査です。検査結果は専用の報告書でお返しし、詳しい解説冊子もご提供します。
認知機能セルフチェッカー
認知機能セルフチェッカーは、あなたの眼の動きを分析して認知機能の状態を確認できる次世代型の検査機器です。口頭や筆記での回答が不要で、負担の少ないところも特徴です。 本検査は、利用者が何らかの病気に罹患している可能性を示したり、診断等の医学的判断をしたりするものではなく、また、本検査に使用される危機は疾患の診断、治療または予防を目的としたものではありません。本検査は、日頃の認知機能の状態を知るためのスクリーニング検査ですので、ご自身の認知機能の状態把握の目安の一つとしてください。
2021 © Shinsenkai Matsuyama Madonna Byoin